激流を泳ぎまくる!!
回想記です♪(⇒過去記事はこちらです)
前回の続きです。
オーストラリアでのラフティングガイドのトレーニングコースが始まって数日は、特に何のレクチャーもなく、素人同然のトレーニング生達はただひたすらタリー川を下りまくっていたのでした。
そして、ありとあらゆるところで転覆しまくり、激流を流され続けたのでした。
今考えると、本当に危ない箇所を流されていましたね・・・
タリー川は、アンダーカットやシーブといった流されると危ない箇所が多数存在する川なのです。
アンダーカットやシーブというのは、激流に点在する岩が作り出すもので、簡単に説明してしまえば、「そこにハマると抜け出せない」といったものだと考えてもらえれば結構です。
(これらはまた別の機会にでも説明したいと思います。実際に私がRNR社に在籍した延べ13年間の間にも「不幸な出来事」は6件も起きてしまっていました)
そして、コースが始まって3日目くらいからは、いよいよトレーニングコース名物と言ってもよい「ひたすら激流を泳ぐ」という訓練が始まったのでした。
これはもう文字通り、単純に色々な激流を泳ぎまくるのです!
コースディレクターのピーターが、
「この激流を、ここからあそこまで泳げ!」といった具合に指示を出し、トレーニング生がどんどん激流に飛び込み泳いでいくのです。
大抵、泳ぐのは激しい激流と決まっていました(笑)
午前中ならダブルウォーターホール、シアター、ステアケースといった岩だらけのグレード4の激流を泳ぐのです。
しかも、このトレーニングコースが行われた1997年5月の時期は雨が多く、いくら常夏の場所とはいえ、山の中のタリーは結構寒かったし、水温もそんなに高いわけではないので、
泳ぐのはものすご~く寒かったのです!
なぜかスイムのトレーニングがある日は決まっているかのように雨が降っていました・・
ラフティングのガイドになるわけなので、「激流を泳ぐスキル」というのは非常に重要なものとなってきます。
「毎週クビが切られるトレーニングコース」の第1週目において、ピーターが各トレーニング生のこの「激流でのスイム能力」を見ているのは明らかでした。
したがって、私はこのスイムトレーニングの時には、いつもガムシャラに泳いでいました(笑)
激流を泳ぐときには、プールで泳ぐような綺麗なフォームでは泳げません。
ライフジャケットを着用している為、浮くのですが、そのかわりに流れを受けやすくなってしまい、水の抵抗をモロに受けてしまいます。
ですから、そんな優雅に泳いでいてはあっという間に下流に流されてしまうのです。(これはあくまでも、普通レベルでの話です。本格的なアスリートスイマーではまた違ったものとなるでしょう)
ですから、流れの早い激流を泳ぐ時には、「回転力が必要」となります。
ようするに、クロールの腕を掻くスピード、バタ足のスピードを上げるわけです。
私はピーターの目の前で「失敗」はしたくなかったので、猛烈に回転力を上げて激流を泳ぐようにしてました。
特に流れの激しいところを泳いで渡るときにはなおさらです。
(後にピーターは「あの時のお前はマシーンのように泳いでいたな」と笑いながら話していました)
渡りきれなかったトレーニング生はあっという間に下流に流されてしまいます。しかも、そのまま危ないところにながされるといったケースが多かったですね。
このスイムトレーニングというのは体力的にも精神的にも最も厳しいものでした。
みんな、その日のメニューにスイムトレーニングがあると分かると思いっきり沈んでいましたね(笑)









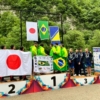




ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません